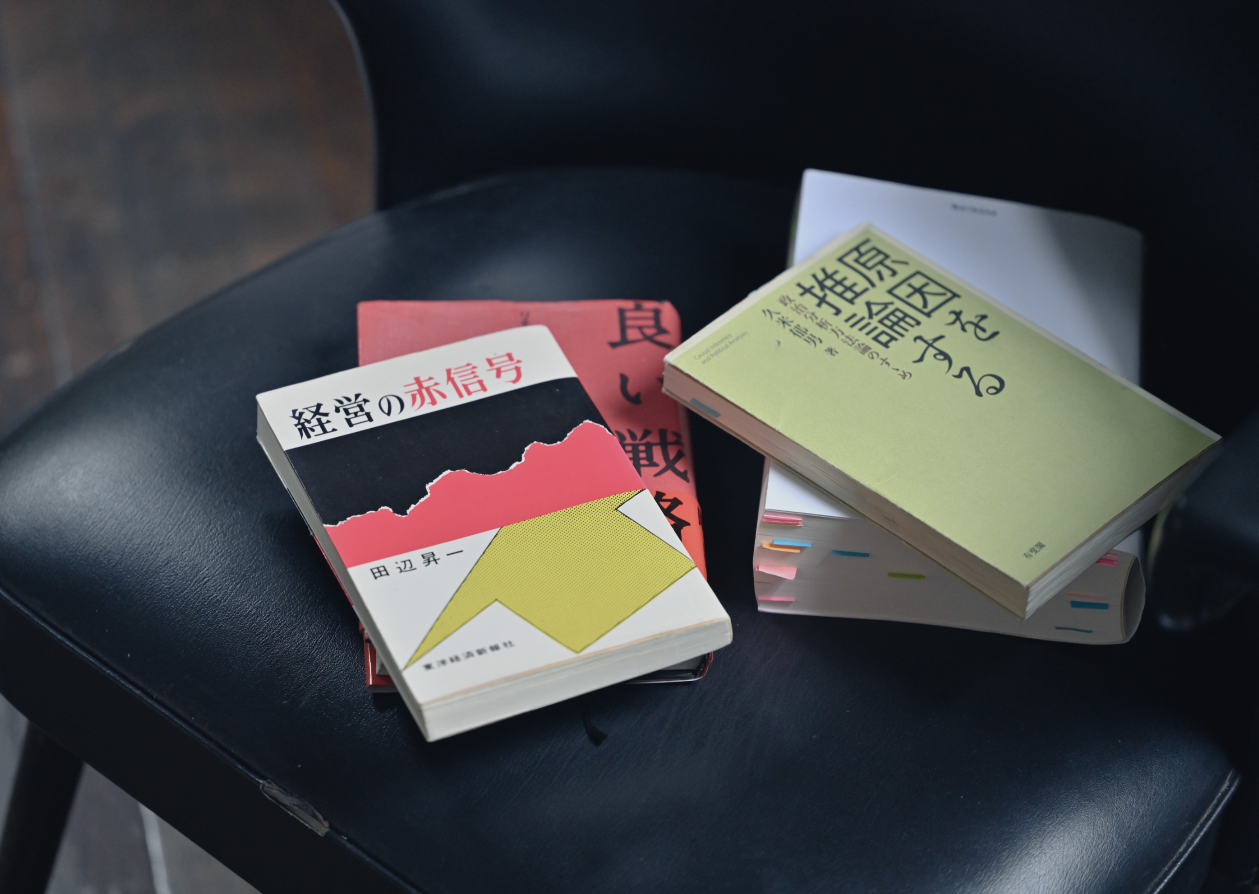
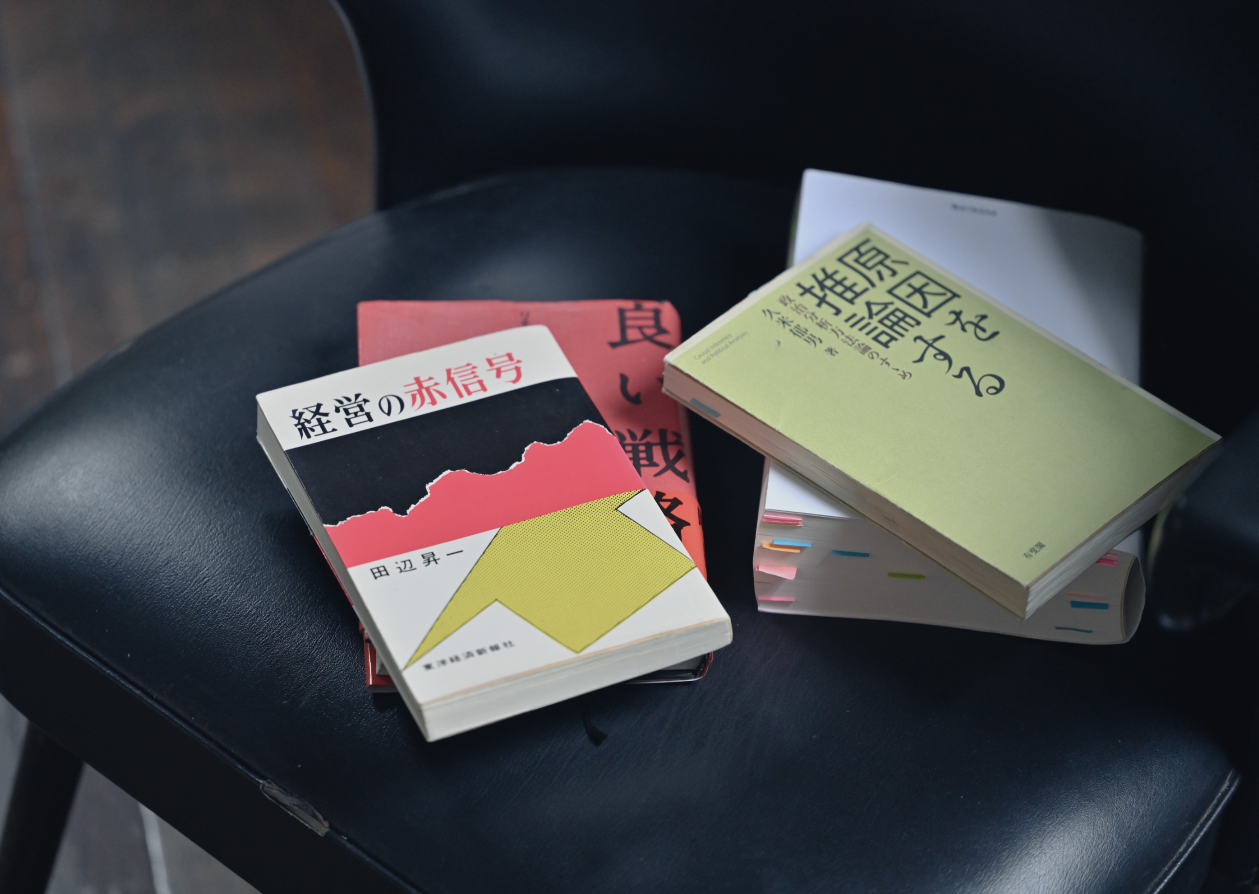
どこを変えれば、
会社は動き出すのか?
その会社の“センターピン”を見つける
「人事制度さえ変えればいい」
「WEBマーケティングの強化で劇的に変わる」
世の中には、そんな情報が溢れています。
つい飛びつきたくなりますが、経営はそれほど単純ではありません。
中堅企業のリソースは限られているからこそ、
最も大切なのは「着手すべき優先順位」を見極めること。
課題は複雑に絡み合い、連鎖しています。
ボウリングで一番ピンを倒せば、他のピンも連動して倒れるように。
経営にも“センターピン”があリます。
今、どこを変え、何を残すべきか。
その判断が、会社の未来を大きく変えていきます。
この判断は、
10年後にどう響くのか?
その瞬間を切り取れば“正解”は誰にでも出せる。
でも、環境は刻一刻と変わっていきます。
変化のスピードが早いからこそ、足元ではなく5年先、10年先を見て判断する。
「この選択は、未来につながるだろうか?」と問い続ける視点が欠かせません。
永く視る
この判断は、
10年後にどう響くのか?
その瞬間を切り取れば“正解”は誰にでも出せる。
でも、環境は刻一刻と変わっていきます。変化のスピードが早いからこそ、足元ではなく5年先、10年先を見て判断する。
「この選択は、未来につながるだろうか?」と問い続ける視点が欠かせません。
組織全体として、何が噛み合っていないのか?
会社は強みで伸びるが、弱みが成長を阻害する。
経営には、戦略・人材・仕組み・社風など多くの要素が絡み合っています。
部分的な最適解が、必ずしも会社全体にとってベストな選択とは限りません。
全体を広く、対極を同時に捉える視点が必要です。
広く観る
組織全体として、何が
噛み合っていないのか?
会社は強みで伸びるが、弱みが成長を阻害する。
経営には、戦略・人材・仕組み・社風など多くの要素が絡み合っています。
部分的な最適解が、必ずしも会社全体にとってベストな選択とは限りません。全体を広く、対極を同時に捉える視点が必要です。
会社の“DNA”に沿った判断か?
会社には歴史の中で培われた“人格”が存在する。
他社の成功事例が、自社にとっても最適とは限りません。
判断の軸となるのは、自社のDNA──強みや文化に沿っているか。
原点に立ち返ることで、本当に“効く”打ち手が見えてきます。
目的は何か、その選択はわが社らしい判断か。
会社のDNAに基づく判断が、“ブレない経営”をつくります。
深く診る
会社の“DNA”に
沿った判断か?
会社には歴史の中で培われた“人格”が存在する。
他社の成功事例が、自社にとっても最適とは限りません。
判断の軸となるのは、自社のDNA──強みや文化に沿っているか。
原点に立ち返ることで、本当に“効く”打ち手が見えてきます。
目的は何か、その選択はわが社らしい判断か。会社のDNAに基づく判断が、“ブレない経営”をつくります。
経営者の隣に立つ
コンサルタントとしてのスタンス
リープコンサルティングのスタンスは、
「上から教える先生」でも「依頼をこなす下請け」でもありません。
経営者の横に立ち、迷った時に横を向けば、そこにいて、
ブレない判断を支える存在でありたいと考えています。
関わり方は、会社ごとに異なります。
会議を引き締める“生簀のナマズ役”になることもあれば、
経営者のジャストアイディアを形にするための壁打ち役になることも。
ソリューションを当てはめるのではなく、
自然と”その会社に必要な在り方”になっていく。
そんな感覚で向き合っています。
その根底にあるのが、禅寺で教わった言葉
「随所に主となれば、立つところ皆真なり」
どこでもリーダーシップを発揮すべきという意味だと理解していましたが、
本来の意味は「その場に馴染めば、どんな状況も理解できる」という意味だと教わりました。
場に馴染み、会社を深く理解したうえで、何をすべきかを一緒に考えていく。
それが、私の考える”コンサルタント”という仕事です。
INTERVIEW
なぜこの仕事に向き合い続けるのか。
岡田個人としての考えを、
語っています。
両親の倒産を経験した子ども時代
なぜ中堅企業こそ支援が必要なのか?
コンサルについてのよくある誤解
コンサルティングの最高のゴールとは?

PLAY MOVIE
